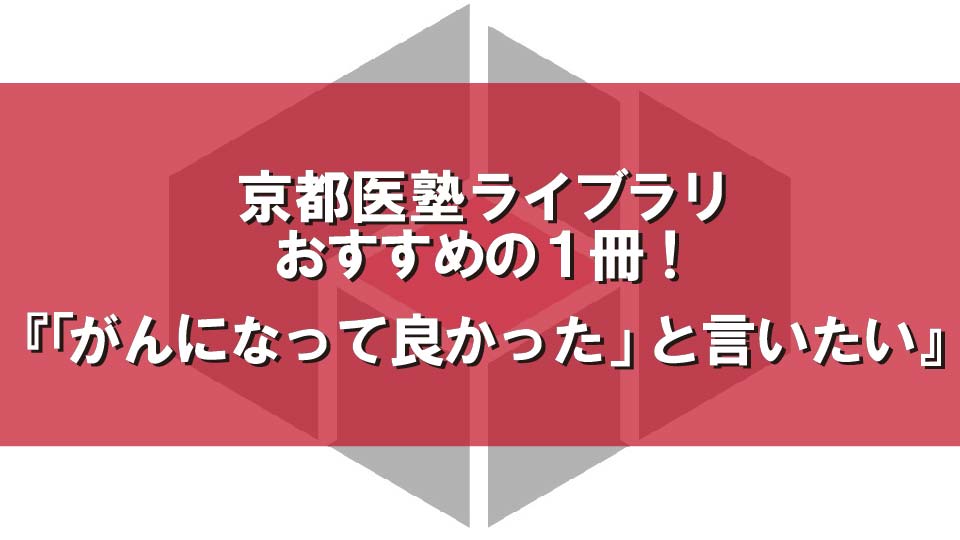「がんになって良かった」と言いたい
著者の山口雄也さんは1997年京都市生まれ。京都市立堀川高校から京都大学工学部に進学した、聡明で快活な青年です。
そんな彼がまず世間の注目を集めたのは、2019年1月。地元・京都新聞の正月号の1面で、彼のブログやSNSでの発信が「若者のがん 不幸と思う?」と題して紹介されたときです。
ところが、その後、この記事が大手ネットニュースに掲載されたところ、批判的なコメントが殺到します。
「もっと過酷な病気になってみてください」
「自分に言い聞かせているだけ」
「生きているから言える言葉だ」
「そう思い込まないと生きていけないだけ」
「がんになって良かったね」
それを見た彼は「辛辣な意見に心を何度も何度も刺され」る思いをしたのでした。
その理由は、記事の題「がんになって良かった」。彼には、そんな安っぽい撞着語法を使ったつもりはありませんでした。
◇
その後、この本を一緒につくることになるNHKディレクターの木内岳志さんに出会い、『ひとモノガタリ』という番組の中で、「”がんになって良かった”と言いたい~京大生のSNS闘病記~」というタイトルで放送がされました。
こちらのほうは非常に良い反響で、多くの手紙も寄せられました。
(僕に宛てられた手紙の)そのうちのひとつに、心を打たれた。
『がんになって良かった、これは意外に多くの方が口にされます。私もその一人です。
受け入れられない人が多いのは、病を『負』として受け入れる風潮と、命に思いを巡らす機会がないからです。病を経て人生を見直す人の声を聞く機会が必要なのです。今回の番組はその点において非常に深いものでした。』
これだ、と思った。僕のなかで忘れていた想いが蘇った。もっと患者の声を伝えなければならない。
これが闘病生活を文章に綴るなかで気づかされたことだった。
2つのブログ
彼は、2つのブログを使い分けていました。
ひとつが、がんが発覚したあとの2016年12月8日に立ち上げた『或る闘病記』。闘病生活の様子や様々な出来事を、多くの画像も交え、意識的に軽妙な調子で記します。
もうひとつが、2016年8月30日、「徒然なるままに」と題する投稿でスタートした『ヨシナシゴトの捌け口』。ブログをスタートした3ヶ月余り後の12月2日、「癌を宣告された。」と告げたのもこのブログでした。
『「がんになって良かった」と言いたい」の由来は、『或る闘病記』の2017年3月20日の記事です。
僕は癌という病気に、この世界の美しさを教えてもらいました。
空が青かったり、パンが美味しかったり、朝気持ちよく起きられたり、
癌という病気は、そんな些細なことで心が満たされるほど幸せになれるようにしてくれたんです。
生きている今この瞬間がどれほど掛け替えのないものなのかを伝えてくれたんです。
そして明日、本当に何事もなく手術を迎えることが出来ました。
だからこそ、こう言えるんです。
ありがとう。がんになって良かった。
本書のタイトルは『或る闘病記』から取られましたが、内容は『ヨシナシゴトの捌け口』を再編したものです。
『ヨシナシゴトの捌け口』は、シリアスで内省的・思索的な内容が中心となっています。がんの闘病生活での心の動きや、友人・知人・患者仲間との出会い、彼らとの思い出、彼らへの思い。それらが、がんという得体の知れない敵を前にした、生への渇望とともに描かれています。
様々な人との出会い・思い出は、本書の圧巻です。
病院のバリスタ、おっちゃん、塾の先生、高校の先生、ピアノの先生、幼い頃からの友人、様々な人が登場しますが、そのどれもが個性的で印象的です。
◇
彼は、文章という形で生きた証を残すためにブログを書きました。
しかし、彼は凡百のブログ・闘病記の書き手ではなく、本書はどこを開いても読む者を離さない引力に満ちています。それは、予後不良のがんとの闘病という壮絶な内容の力だけではなく、言葉を残すことに対する彼の強い思い、その必死さが生み出す筆力に拠るところが小さくありません。
ながらくブログを書いていると、一時間で三〇〇〇字程度は書けるようにはなった。それでも、京都市立紫野高校在学中にして文藝賞を取り、自分より若い十九歳最年少で芥川賞を取った綿矢りさにはなれない
との一節は、書くことへの執念を感じさせます。
1度目
この本は、彼の4度におよぶがんとの闘いが背景になっています。
1度目は、2016年11月、19歳の秋。肺炎がきっかけとなり、縦隔原発胚細胞腫瘍という予後不良の希少がんが発覚したこと。京大病院に入院し、がん闘病生活が始まりました。
なんで俺なんだろう。
この数週間で気が狂うほど繰り返した。
どうしてあなたが。
この数週間で誰しもがそう言った。
そんなものに対する答えなんてないのに。
がんに見舞われたことで、思い悩む日々が続きました。なかでも「死」を強く意識することに。
なぁ、こんなこと聞いていいんか分からんけど、もし、本当に死ぬことになったら、どうする?
こんな問いかけに彼は考えます。
本当に死ぬことになったら、僕はどうするのだろうか。反芻の果てに飲み込むことさえできず、吐き出しそうになる問いに悶え苦しんで、そうして気が付いたら寝ていて朝が来ている。あれ以来、そんな日が幾夜かあった。
しかしながら、死ぬことを決定づけられたわけではなかった。紙一重で異なる次元にいた。自分には、まだ生きる希望がいくらか広がっていた。近々死ぬことが分かって生きるということは、今の自分の生き方とはまた別次元なものなのだ。
本当に死ぬことになったら、どうするのだろうか。
2度目
2度目は、2018年6月に発覚した白血病。
「京大へ定期検診へ行き、血だらけの歯茎を見せると、主治医は蒼ざめた。すぐさま血液内科に通され」、その結果は「血液内科医も驚く数値だった」。急性白血病、緊急入院。
がん患者にとって一番ショックが大きいのは、最初のがんの発覚以上に、再発の際のそれであると聞きます。
彼は、白血病という事実を突きつけられたことにより、「この四日を、人生で最も混乱した四日間として過ご」すことになりました。
2年前、最初にがんが見つかった際、死を意識し、
五年以内に死ぬだろうと思って生きることの恐怖と失望とは、あなたには決して分からない。なぜなら自分にもさっぱり分からなかったからだ。
もう二度とクリスマスが訪れることはないだろうと感じながらクリスマスソングを聴く人間の気持ちがわかるだろうか?
二十回目の誕生日を迎え、食卓を囲んで親と酒を飲みかわした。
うまかった。うまかった。泣きそうになるほどうまかった。
と言っていた彼をして、
動悸がして、視界は螺旋を描いた。それは、未だかつて感覚したことのない、死の形象だった。
と言わしめるものでした。
その後、夏に骨髄ドナーが見つかり、京大病院で白血病治療のための移植を受けることに。
移植手術を受けた2018年10月のブログで彼は書きました。
二十一歳の誕生日プレゼントは、命だった。
ギフト、と呼ぶ方が正しいかもしれない。
特別な、そして特殊な贈り物だ。値札や包装はない。無論どんな店に並ぶこともない。
プライスレスな「赤いギフト」。
命を助けてくれた骨髄ドナーに感謝して、彼は書きます。
この世界は、きっと厳しさと同じくらい、優しさに溢れているのだ。僕の想像を遥かに超えて。
3度目
3度目、2019年春、白血病の再発。
移植を受けたドナー由来の血細胞が減少し、94%の細胞に染色体異常があることが発覚したのです。
そこで示された選択肢は、再移植。ただし、その選択は過酷なものでした。
「死ぬかもしれないAと、死ぬかもしれないB」の選択。
選択肢Aは、まもなく血液ががん化するのは確実だが、このまま放っておく。既に厳しい治療を受けているし、まもなく体力的な限界値も迎える。
選択肢Bは、「ハプロ移植」。HLA(白血球の型)が半分一致した血縁者などがドナーになる移植方法で、HLAが完全一致するよりもがん細胞を攻撃する効果が高いものの、患者の身体を攻撃する作用も強いため、リスクも大きい。5年生存率は3割から4割。
その夜、僕は自室で泣いた。
死から逃げるために、死の胸元へ飛び込まねばならないという矛盾が、そして理不尽が、僕を激しく混乱させていた。
しかし、彼はハプロ移植を受けることを決め、移植を受けられる兵庫医科大学に転院することになります。
新天地に赴き、新しい主治医と出会った。
君のことを生きて親元に返す、それが私の使命です。
主治医はそう力強く言い放ってくれた。
母をドナーとして行ったハプロ移植は成功。
しかし、その後、激しい副作用に苦しむことになります。
髪の毛は一本も残さず抜け落ちた。三回目だった。
一度は退院をしますが、間質性肺炎を発症して入院。移植患者によく見られる、ドナー幹細胞由来の白血球が患者の体を攻撃するもの。
母の細胞が僕のことを攻撃していることに、耐えられなかった。それだけは、ただそれだけは、死んでも死にきれないと思った。
2019年12月には退院。しかし、その2週間後には再び入院することになります。
しかしながら今度の肺炎は、データ上にのみ存在する非常に奇妙な肺炎だった。酸素飽和度は大抵90%台の半ばを行き来していて、ほとんど正常値に近かった。そして肺の影はそこまでひどいものではなく、実際のところ呼吸もさほど苦しい状態ではなかった。--〈中略〉--ただ一つおかしい点があるとするのなら、体内の炎症反応を示すCRPという値のみが、正常値の十倍以上を示していたということだ。つまり、母からもらった白血球が、僕の体内で何かと戦っているということだった。
4度目
4度目。
「奇妙な肺炎」による入院の後、主治医から白血病の再発を告げられます。
暗がりの病室でイヤホンをして紅白を眺めるほど虚しいものはない。
時計はひっそりと針を進め、病室は誰にも祝われることなく静かに年を越した。
『僕が死ぬ年だ』
3度目の再発。今度こそは死が避けられないのではないかという観念。
そんな絶望的な状況に彼は打ちひしがれます。
この日から、僕は薬を捨てた。
少しずつ、少しずつ、病室のごみ箱の中に、生きるための錠剤を投げ入れた。
この後、病院側と面談が行われ、治療は続けることになります。
二時間の面談が終わったあと、震え続ける僕の肩を母は何も言わずにそっと抱いてくれた。
僕は母から造血幹細胞をもらい、そしてそんな母の愛を裏切ったのだ。
まだ生きていてもいいのだろうか。
やがて炎症が治まり、退院が見えてきます。
退院の朝がきた。曇天の中に青い空が少しばかり覗いていた。それでも、心の中には少しの晴れ間もなかった。喜ぶことが、いずれ訪れる悲しみを肥大化させてしまうのだ、と僕は自身に言い聞かせた。
そして迎えた主治医の回診。主治医は、「いつも悪いことばかりだから、今日は良い事を教えてあげよう」と告げます。その結果は……
再発したがんが……消え…た?? ん、ですか?
◇
そんながんの消失・退院にも、彼は冷静でした。その理由はもちん、それまでも治癒と再発を繰り返してきたから。
助かったことは手放しになんて喜べやしない。これまでもそうだったし、きっといつまでもそうだ。
彼は、もう幾度目か分かりません、「生きていることの素晴らしさ」について記します。
自身の境遇をぐちぐち言う自分が、いかに愚かであるかを思い知らされた。僕はまるで何も分かっちゃいない。この世に生きているということが、どれほど素晴らしいかということについて、これだけの経験をしたのに、まだ何も分かっちゃいない。
僕はおそらく、とんでもない力によって生かされている。
理由は分からないが、とにかく、”生かされて”いるのだ。
エピローグ
この本が出版されたのは2020年7月。ここで、その後のことを簡単に記したいと思います。
2020年12月、彼は、急性骨髄性白血病を発症し、2度目のハプロ移植を受けることにします。
また、この頃から献血・輸血の啓発にも積極的に取り組みます。
2021年3月には「献血で輝くいのち」という講演動画作成に協力。同月には、2回目のハプロ移植を受けます。
2021年4月には「祈りの献血、命の輸血」というブログ記事とSNS投稿を公開し、その”過激な”表現に批判が集まります。しかし、これで彼の存在が注目を浴びることになりました。
2021年6月6日。この日、山口雄也さんは旅立たれました。