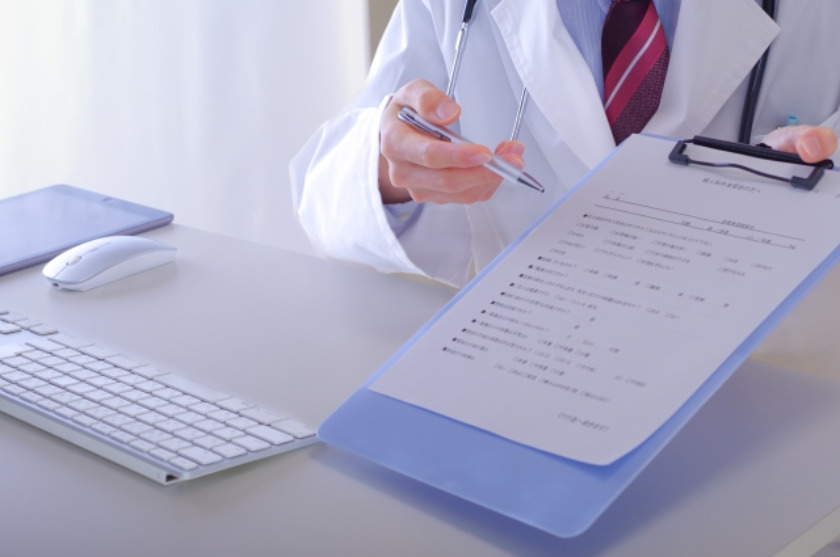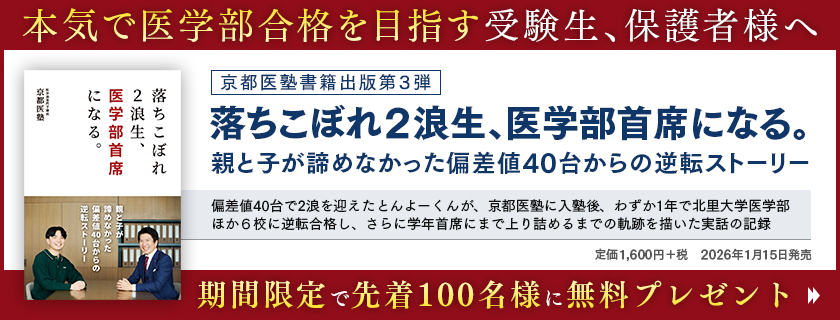医師免許取得後、医学部卒業生はまず臨床研修を経験します。
この研修に参加する医師を『研修医』と呼びます。
研修医期間は、医師として基本的な診療技術や知識、マナーを身につけるための大切なステップで、原則として2年間行われます。
研修医は担当指導医の下で実際の患者を診察しながら学び、その経験を通じて医師としての能力を高めていきます。
目次
研修医とは?医師免許取得後の研修期間

研修医とは、医師国家試験に合格し、医師免許を取得した後に「初期臨床研修」を受けている医師のことです。
厚生労働省の制度(医師法第16条の2)により、全国の研修病院で原則2年間の臨床研修を行うことが義務づけられています。
この研修期間中、研修医は医師法に基づき研修医期間を修了するまで一人前の医師として独立して診療することは認められず、担当指導医の指導の下で診療を行います。
研修の目的は、幅広い診療科目を経験して臨床判断力と技術を養い、医師としての基礎力を固めることにあります。
アメリカの研修医の違い
日本の初期研修医制度に対し、アメリカでは「インターン」という1年目の研修医制度があります。
アメリカのインターンも臨床経験を積みますが、プログラム期間は一般的に1年間と短めです。
アメリカでは研修医にも給与が支払われますが、その額や給与体系は病院によって差があります。
なお、日本の研修医制度は2年間かけて全身的に基礎を学ぶのに対し、アメリカでは主に1年目に基礎診療を学び、その後専門医研修(レジデンシー)に進むという違いがあります。
研修医の働き方
研修医は大学病院や地域の病院に所属し、担当指導医のもとで診療に携わります。
勤務スタイルとしては、外来診療や病棟回診、手術補助、当直など多岐にわたる業務を行いながら、医療現場での経験を積むことが求められます。
研修病院によっては夜間勤務や休日出勤もありますが、過重労働を避けるために法律で時間外労働の上限が定められており、働き方改革により勤務時間の管理がより厳格になっています。
研修医の主な仕事は、担当指導医の指導のもとで、さまざまな診療行為を実践することです。
具体的には、患者の問診・診察、身体所見の確認や各種検査(心電図検査、聴力・味覚検査など)を行います。
一方で、研修医が単独で行える診療行為の範囲は限られており、内視鏡検査や動脈穿刺、全身麻酔の管理といった高度な医療行為は原則として許可されていません。
研修医は医師である一方で学び手でもあるため、すべての処置や診療には必ず指導医や上級医の許可・監督が必要です。
言い換えれば、患者に影響を与え得るすべての診療行為は上司の了承を得て初めて行えることが前提となっています。
また、研修医は医療技術だけでなく、勤務中の服装・言葉遣い、患者対応といった態度面でも評価を受けます。
例えば、常に清潔な白衣を着用し、患者や家族に対して礼儀正しく接することが求められます。
担当指導医らは診療スキルだけでなく、研修医の人柄やチーム医療への貢献度についても厳しく指導し、総合的な医師としての成長を図ります。
研修中の注意点
研修医とは、どういった働き方をするのかという点について把握したところで、研修中における注意点についても押さえておきましょう。
アルバイトは禁止
初期研修中は研修に専念する義務があるため、原則として病院以外でのアルバイトは禁止されます。
医療法や関連規定により、病院勤務の医師が兼業をすることは原則認められていないため、多くの病院では研修医のアルバイトを制限しています。
研修期間中は学びの機会を最大化することが重視されるため、報酬を求めて別の仕事に時間を割くことは基本的に許されません。
保険の加入も検討する
研修医は責任ある業務をこなす中で激務にさらされることもあります。
そのため、病気や事故で休業せざるを得なくなった場合に備え、医師向けの休業補償保険(保険医休業保障共済など)に加入することが奨励されます。
また、万が一医療ミスによる訴訟に発展した際に備えて、医師賠償責任保険に加入しておくと安心です。
これらの保険は自己負担の軽減に役立ち、不測の事態でも精神的・経済的な負担を減らす「万が一の備え」として有効です。
研修医の年収・給料は?
研修医は正式な医師として雇用されるため給与が支払われます。
厚生労働省の2011年度調査によれば、初期研修1年目の平均年収は約435万円、2年目は約481万円でした。
この全国平均は長らく更新されていませんが、より近い参考値として、経験年数1〜4年の医師(主に初期研修修了後の若手医師)の平均年収は、賃金構造基本統計調査(2023年)によると約764万円です。
ただし、実際の給与は病院の規模や地域、当直手当の有無などにより大きく差がある点に注意が必要です。
後期研修医との違い
初期研修(卒後1・2年目)を終えた研修医の多くは、より専門的な技術を学ぶ後期研修へ進みます。
後期研修医は2018年から「専攻医」と呼ばれ、希望する診療科の専門研修プログラムに参加します。
後期研修期間は一般的に3年以上とされ、初期研修医とは異なり、病院内でも診療の中核を担う立場となります。
専攻医になると、指導医の一員として後輩の研修医に助言する機会も増え、責任も重くなります。
専門医を目指せる「新専門医制度」
2018年に開始された新専門医制度では、研修医は初期研修後に「基本領域」と呼ばれる19の診療科(内科、小児科、外科など)から専攻する科目を選び、3~4年かけて「基本領域専門医」を目指します。
基本領域の専門医資格を取得した後は、さらに24の「サブスペシャリティ領域」(消化器内視鏡、呼吸器外科、放射線治療など)から追加的に専門性を磨くことも可能です。
このように、後期研修(専攻医)のステップを経て、医師はより高度な専門医としてキャリアを積み重ねていきます。
研修医は医師としての最初のステップであり、初期研修中は多くを学び、経験を積む期間です。
今回解説したように、研修医としての働き方や注意点、待遇について理解した上で、初期研修病院やその後の進路を選択しましょう。
本気で医学部合格を目指すなら医学部専門予備校 京都医塾
 研修医として患者さんの前に立つ未来を思い描いたら、その前に越えるべきは医学部入試です。
研修医として患者さんの前に立つ未来を思い描いたら、その前に越えるべきは医学部入試です。
本気で医学部合格を目指すなら、医学部専門予備校 京都医塾がおすすめです。
独自の完全個別カリキュラムや寄り添いサポートの独自システムであなたを強力にバックアップします。
13名チームで弱点を徹底補強
医学部専門予備校 京都医塾では、講師13名がチームを組み、あなたの学力データを多角的に分析し、弱点を克服できることが特徴です。
学習の進捗と生活リズムをチェックして学習効率を最大化します。
学力・メンタル・生活管理を一体で支える体制だから伸び悩みを解消し、合格可能性を高めます。
常に「いま必要な勉強」が可視化されるため、受験当日まで迷わず走り切れます。
完全個別カリキュラムで最短合格
医学部合格に必要な科目・配点は大学ごとに大きく異なります。
医学部専門予備校 京都医塾では志望校と現在の成績から逆算した「合格最短ルート表」を作成し、1週間単位で学習計画を提示します。
得意科目は先取りで難問演習に集中し、不得意科目は基礎穴埋めから段階的に強化します。
カリキュラムは毎週見直すため、模試や学校行事で予定がずれてもすぐにリカバーすることが可能です。
寄り添いサポートで挫折を防ぐ
浪人生活の大きな敵は孤独とモチベーションの低下です。
医学部専門予備校 京都医塾の寄り添いサポート体制は、学習面だけでなく食事・睡眠・メンタルまで細かくケアします。
講師の進捗確認や悩みの共有、生活リズム指導で体調をキープし、定期カウンセリングで不安も軽減します。
常に誰かが見守ってくれる安心感が、最後までやり抜く原動力になるでしょう。
まとめ
今回の記事では、医師免許取得後に行われる2年間の初期臨床研修、いわゆる研修医の実態を、仕事内容・年収・働き方から後期研修医(専攻医)との違いやアメリカの研修制度まで詳しく解説しました。
研修医は指導医のもとで幅広い診療科を経験しながら臨床スキルやマナーを磨く重要な経験ですが、長時間勤務やアルバイト禁止など厳しい一面もあります。
こうした現実を知り、医学部受験を目指す皆さんの中には「自分にやり遂げられるだろうか」と不安を感じた方もいるのではないでしょうか。
しかし、医学部専門予備校 京都医塾なら、13名チーム制による徹底指導と個別カリキュラム、そして手厚いサポートで学力面も精神面も万全に整え、医学部合格までの障壁を一つひとつ取り除いていけます。
さらに、1泊2日医学部合格診断ツアーでは、マンツーマンの体験授業や校舎・寮見学で学習環境を確認できるだけでなく、プロ講師が現在の学力を無料で分析し、最適な学習プランを提案します。
宿泊費・交通費は無料なので、遠方からでも安心してご参加ください。
迷っている時間を行動に変えてみませんか。