医学部に入学した後は大学の課程をこなすのはもちろん、医師国家試験を受けたり研修医としていくつかのカリキュラムを修めなければなりません。
しかし、通過するプロセスが多すぎて、医師として活動するためには何年くらい必要なのか分かりづらいと感じている人も多いでしょう。
そこで、今回は医学部に入学してから医師になるためには何年かかるのか、その年数について解説していきます。
医学部は何年で卒業できるのか?

医学部は経済学部や文学部などの学部よりも卒業までの年数がかかることで有名ですが、いったいどれくらいの期間、大学に通う必要があるのでしょうか。
こちらの項では、医学部において卒業までにかかる年数について解説します。
6年で卒業
医学部は、卒業までに原則6年かかります。
1年次は一般教養を学ぶことが多く、それと並行して医学の基礎となる知識も学んでいきます。
総合大学の場合、1年次は他学部の学生と一緒に授業を受けることも多く、幅広い分野に触れることができます。
2~4年次になると基礎医学だけでなく、臨床医学や社会医学などの専門性の高い内容を学ぶ講義も増えていきます。
一般的に、4年次の最後に共用試験と呼ばれる試験を受験し、それに合格することで臨床実習への参加資格が得られます。
臨床実習では、大学病院や総合病院の各診療科をグループでまわり、基本的な診察の知識や技術などを学びます。
臨床実習は5~6年次に行われることが多く、それまで講義や演習で学んできた知識をより実践的なものにしていきます。
そして、6年次の2月に行われる医師国家試験に合格すれば、医師の資格を得ることができます。
大学によっては細かなカリキュラムが異なる場合もありますが、医学部の6年間は大まかにこのような流れで進みます。
留年することもある
意外に思う人もいるかも知れませんが、医学部では留年することも珍しくありません。
文部科学省が行った調査によると、平成26年度医学部入学者のうち6年で卒業した人の割合は国立大学医学部で85.2%、公立で87.5%、そして私立では81.1%となっています。
国公立大学と私立大学の全ての医学部の平均値は83.9%で、100人中およそ16人の学生が留年している結果となりました。
留年してしまう学生が多いのは、授業や試験の難易度が高く、必修科目を落として単位が取れなくなってしまうなどの理由があるようです。
医師になるまでの試験

医学部合格後、医師になるまでにはいくつかの試験をパスしていく必要があります。
1つ目は卒業試験、2つ目は医師国家試験、そして共用試験です。
こちらの項では、これらの試験について深掘りしつつ見ていきましょう。
卒業試験
みなさんもご存知のとおり、医師国家試験を受けるには、まず医学部を卒業する必要があります。
そして、卒業するための関門として課されるのが卒業試験です。
卒業試験を突破できない学生は留年してしまい、次のステップに進むことができません。
医学部の卒業試験は科目数が多いのが特徴で、少なくとも10科目、大学によっては30科目もの試験が課されることもあります。
また、医学部の卒業試験は長期にわたって実施されることでも有名です。
医学部の卒業試験は、通常9~12月頃を目途に実施されますが、概ね1~3か月間もの長いスパンで行われます。
もちろん、大学によってテスト期間は変わってきますが、普段以上に勉強に追われる日々が続くので、学生の負担は非常に大きいものになります。
さらに、多くの学生が医師国家試験の対策も並行して開始している時期ですから、試験期間における生活の激変は避けられないでしょう。
このように、他学部では卒業論文や単位修得のみで卒業できる一方で、医学部では卒業までに大きな壁を乗り越える必要があるのです。
学生によってはこの試験でつまずいてしまい、何年も留年してしまうこともあります。
過去問などを利用して、必ず医学部を卒業できるよう勉強に励みましょう。
医師国家試験
卒業試験に合格した後に待っているのが、医師国家試験です。
こちらの試験は、医学部で6年間学んだ成果を確認し、医師になるための実力の有無を判定するために実施される試験です。
医学部の卒業試験と同様、こちらの試験もクリアしないと次の段階へは進めません。
何年も落第していると、同期に後れを取ってしまいますので1回でパスする意気込みで臨みましょう。
こちらの試験は、毎年2月頃に2日間にわたって実施され、医学部の卒業試験に合格した人と合格の見込みのある人に受験資格が与えられます。
また外国の医学部を卒業し、外国で医師免許を取得した人の中で、国から許可された人も対象となります。
受験資格の詳細は厚生労働省のホームページで確認できますので、興味のある人はチェックしてみるとよいでしょう。
そして、出題科目は、臨床現場の想定問題はもちろん、循環器、呼吸器、感染症、整形外科など極めて多岐にわたって出題されます。
マイナーなジャンルからも出題されることが多く、放射線に関する問題や麻酔に関する問題を筆頭に、色々なカテゴリーから幅広く出されます。
この他、法律問題なども課されますので、相当な量の知識を蓄えておく必要があるでしょう。
共用試験
2000年代に入り、医学部では共用試験と呼ばれる試験も実施されるようになりました。
この共用試験は臨床実習前に行われる実力判定試験の一種で、CBTとOSCEと呼ばれるものが実施されます。
この試験に不合格となった学生は臨床実習をさせてもらえないだけでなく、ひどい時は留年させられてしまいます。
つまり、こちらの試験も医師となるためには避けては通れない試験なのです。
OSCE
OSCEは、医学部の学生が臨床実習に参加するにあたり、十分な臨床能力を有しているか判定するために行われる試験です。
この試験では、知識が問われるというよりは、基本的な診察の技能や態度などの実践的な部分が評価されます。
こちらの試験は医学部ごとに実施する時期に違いがあり、早い医学部では3年生に、遅い医学部では4年生の時に行われます。
試験範囲については全国共通で、
・医療面接
・胸部、全身状態とバイタルサイン
・腹部
・神経
・頭頚部
・基本的臨床手技、救急
の6項目が出題されます。
各課題に患者の設定や診察項目の指示が用意されており、模擬患者さんを相手に試験を行います。
それぞれの試験時間は医療面接が10分、他の科目は5分です。
科目によっては診察項目が多いため、制限時間をオーバーしてしまわないよう日ごろから十分な訓練を積んでおきましょう。
評価項目も公開されていますので、頭に入れておくと良いでしょう。
CBT
CBTは学生の知識や技能、問題解決能力を判定する目的で行われる試験です。
こちらの試験では学生一人ひとりが専用のコンピューターを使って、画面上に表示される問題を解いていきます。
この試験では、学生ごとにランダムで問題が出題されるので、それぞれが違う問題を解答していくことになります。
CBTの能力が高い人は災害医療の分野で重宝されますので、そちらの道に進む予定の人はより熱心に訓練に取り組んでください。
2020年から2つの共用試験が公的化されることに
厚生労働省の決定により、2020年からOSCEとCBTの2つの共用試験は公的化されることになり、加えてこれまでは評価が一定でなかったOSCEも、評価レベルが標準化されるようになりました。
また、試験が公的化されることで法整備がなされ、診療参加型臨床実習のさらなる促進が期待できると見られています。
医学部の共用試験は公的化がなされるまでに何年もかかってしまいましたが、この度正式に国からのお墨付きをもらうまでに進展したのです。
医師になるまでには何年かかる?

医学部を卒業してから医師になるまでには、何年くらいかかるのでしょうか。
自分のキャリアプランを考えるうえでも、医師になるまでに何年かかるのかしっかり把握しておきたいところでしょう。
ここでは、医学部卒業から医師になるまでに何年かかるのかについて、詳しく解説していきましょう。
最低2年間の研修医期間は必須
医師国家試験をパスし医師免許を取得した後は、2年間の研修医期間が始まります。
こちらの研修を受けないと診療行為をすることができません。
初期臨床研修を修めることで保険医登録が認められ、初めて診療行為の許可がおりるのです。
ただし、基礎研究などを続け、診療に従事する予定がない場合は、研修を受ける必要はないとされています。
初期臨床研修の内容
初期臨床研修では大学病院、もしくは厚生労働大臣の指定する医療機関で2年間の研修が実施されます。
この初期臨床研修では、一般的な診療に対処できるスキルを身に付けるためのカリキュラムをこなしていきます。
研修において必修科目となるのは地域医療、救急、内科、外科、産婦人科、小児科、精神科の7科目です。
この他にも、一般外来における研修が必修となっています。
初期臨床研修中は医学部時代とはひと味違う環境に晒され辛い思いもしますが、何年も続くものではありません。
これから始まる医師としての人生のうち、たったの2年間ですから頑張って乗り越えましょう。
3~4年の後期臨床研修で専門性を高める
2年間の初期臨床研修を修めた後は、3~4年間の後期臨床研修が行われます。
こちらの研修の目的は、自分が希望している診療科に対する知識や技能をより高めることです。
後期臨床研修は初期臨床研修と違い法律で義務化はされていませんが、ほとんどの医師がこちらの研修も受けています。
後期臨床研修の内容
後期臨床研修では、病院ごとに定められている研修コースを受けるのが一般的です。
急性期病院で研修を受ければより多くの症例を経験できますし、複数科で学びたい人にはローテーションを組んで色々な科を回らせてくれる病院もあります。
病院のホームページには研修内容が書かれていますので、情報収集をして自分に適したところを選びましょう。
そして、後期臨床研修を修了すると専門医を名乗れるようになり、報酬と医師としての地位が高くなります。
医師免許の取得後は診察などを通じて何年も患者と向き合うのですから、知識とスキルをより養うためにも後期臨床研修はぜひ受けておきましょう。
医学部に入学してから「医師として働く」まで10年以上かかることも
ここまで、医学部に入学してから医師として働くまでの道のりは、決して簡単なものではないことがわかったのではないでしょうか。
基礎研究医として研究を続けるなどの場合を除き、医学部に入学してから「医師として働く」まで、基本的には8年程度かかります。
後期臨床研修を入れると10年以上もかかるので、何年にもわたって勉強期間が続きます。
編入の場合は例外もあり
みなさんは「学士編入」という言葉をご存知でしょうか。
学士編入とは大学の2年生、または3年生に他大学へ編入できる制度です。
また、一部の大学では1年生の後期から編入できる場合もあります。
医学部は通常、卒業までに6年間要しますが、こちらの制度を利用することで卒業までの年数を短縮できるようになります。
医学部卒業後の進路

何年もの年月を費やし医学部を卒業した後は、学生ごとにそれぞれの進路に進むことになります。
ここから先は、医学部卒業後の進路について解説していきましょう。
様々な選択肢がある
医学部を卒業し初期臨床研修などを修めた人は、そのまま病院に勤務したり、あるいは開業医となったり様々な進路に進みます。
この項では、医学部を卒業した人の進路についてパターンごとに見ていきましょう。
病院勤務
医学部生の進路としてポピュラーなものが、病院勤務です。
研修を受けた病院や、自分の専門性を高めてくれる病院など様々な選択肢の中から自分に見合った施設を選んで勤務先を決定しましょう。
開業医
資金的な余裕がある人は、開業医の道を進むこともあります。
開業医は病院勤務と違い、スケジュールの自由度が高いため身体的負担が軽いのが特徴です。
大学病院
地域枠推薦の場合、そのまま指定の大学病院に留まるケースもあります。
自治体にもよりますが9年前後勤務する義務が課されます。
学費を返還すれば拘束期間の免除も可能ですが、都道府県の同意なく地域枠を離脱した場合には、従事要件のかかっている都道府県以外で専門医を取得することは原則不可となっています。
また、そのような地域枠離脱者を採用した病院に対してはペナルティが課されることもあるようです。
いずれにせよ、地域枠推薦で入学すると卒業後のキャリアがある程度制限されてしまうと言えるでしょう。
医者以外の道も
医学部卒業後の進路は、医師だけとは限りません。
こちらの項では、医師以外の道にはどのような進路があるのかについて解説しましょう。
研究者、就職、企業など
先ほども触れたとおり、医学部を卒業した後の進路は医師以外にも色々なものがあります。
例えば、研究者として義足などの医療工具を作る医工学の分野に進む人もいますし、医療のAI化を推進する医学情報学の分野に進む人もいます。
企業に就職する人もいますし、経営者として成功を収めている人もいるでしょう。
このように、医学部を卒業した後の進路には多種多様なパターンがあるのです。
まとめ
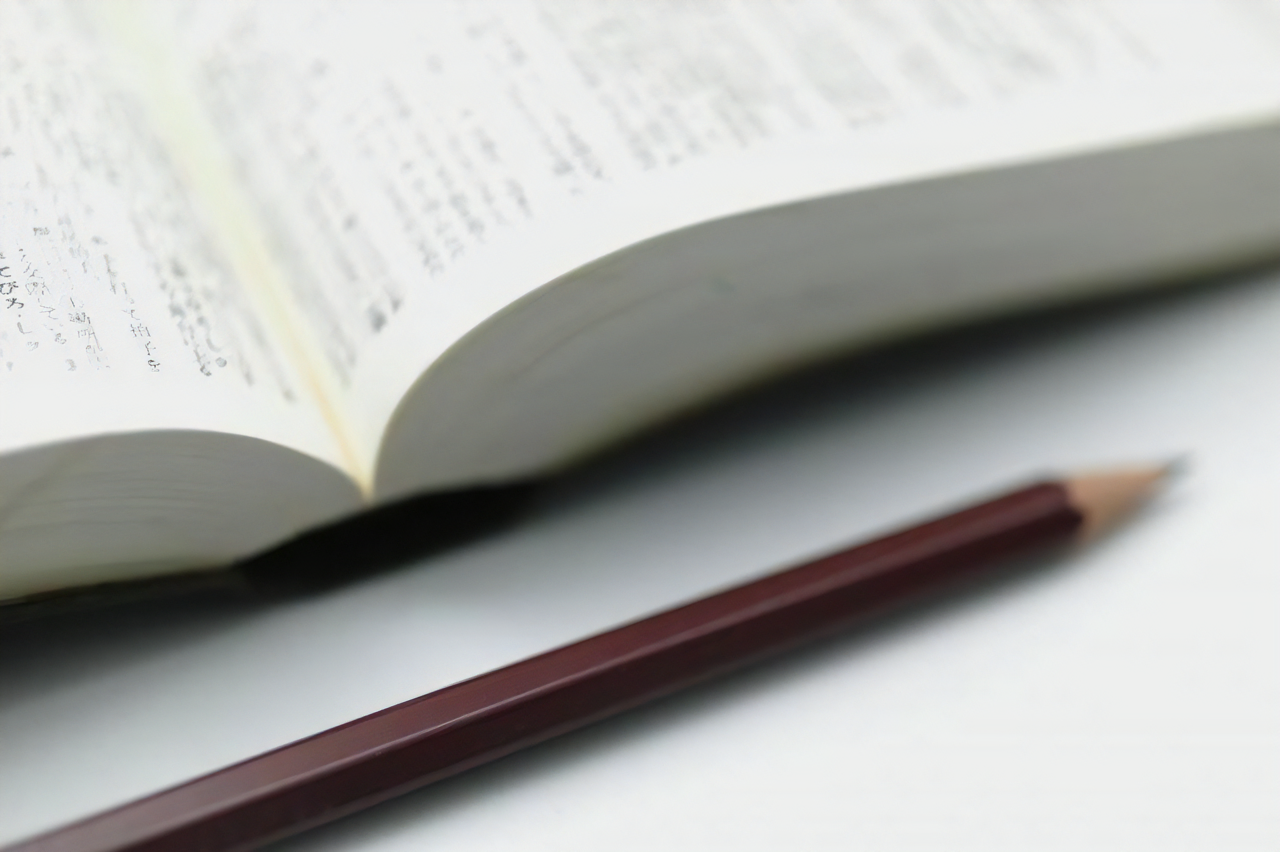
医学部では入学後、基本的に6年間で卒業します。
そして、6年間のカリキュラムをきちんと修め、晴れて卒業した人は医師国家試験を受ける権利が与えられます。
こちらの試験は科目数が多いうえに出題範囲が広いため、しっかりとした対策が必要です。
また、医師国家試験をパスした後は、2年間の初期臨床研修の期間、医師としての基礎を学んでいきます。
研修医の期間は激務と向き合う必要があるため、身体の調子を整えておきましょう。
初期臨床研修を修了した人は、3~4年間の後期臨床研修に進む権利が与えられます。
後期臨床研修は義務ではないものの、スキルアップやキャリア形成に役立つため多くの人がこちらの研修も希望します。
ここまでの過程を修めるために必要な年数は、およそ10年程度です。
何年間も勉強する必要がありますが、一人前の医師になれば病院勤務はもちろん開業の道も開かれます。
現場に出てから何年か経過した後に、「苦労はしたけど、今ではよい思い出だ」と実感できる日もきっと来るでしょう。
あなたが立派な医師になって、ご自身の思い描いた人生を歩んでくれるよう祈っています。


