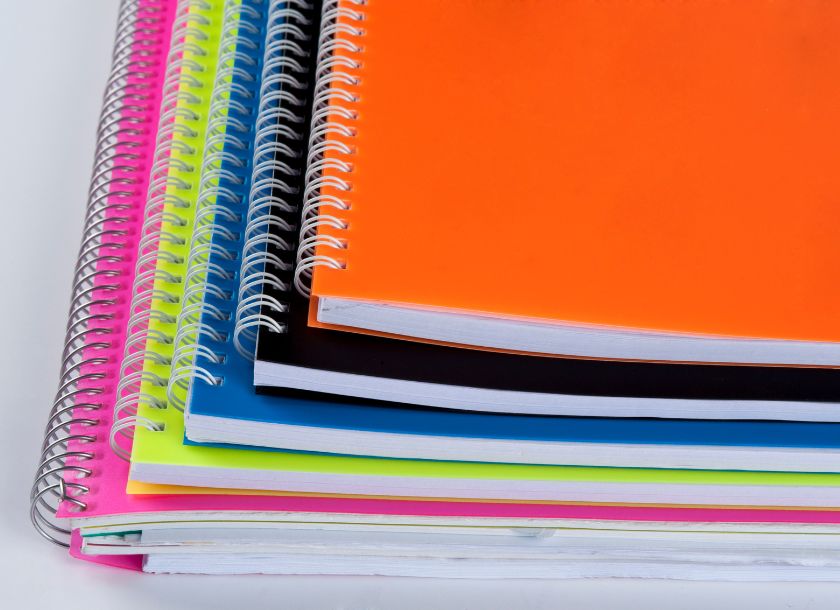ノートの色分けは書き込んだりマーカーしたりする方法がありますが、うまく取り入れることで効果的に復習できるノートに仕上がります。
自分にとってわかりやすいルールで、重要な部分が目立つノートづくりを心掛けることが大切です。
今回の記事ではノートの色分けについて、ルールづくりのヒントや色分けするメリット、その他のノートづくりのコツまで紹介します。
ノートづくりのコツを知りたい受験生は、ぜひ参考にしてみてください。
ノートの色分けは3色がおすすめ!ルールづくりのヒントとは
ノートの色分けは、3色程度に絞るとバランスが良く、見やすさが保ちやすくなります。
ノートの書き込みやマーカーに使う色が多すぎると、ごちゃごちゃして見づらくなる可能性があるからです。
自分流の色分けのルールを作っておけば、パッと見たときにその部分にどういった意味があるのか判断できます。
ここからはノートの色分けルールのヒントとして、「カラーボールペン」と「蛍光ペン」の色分けの例を紹介します。
今回の記事を参考にしつつ、自分なりにアレンジしてルールを作ってみましょう。
カラーボールペンの場合
カラーボールペンの色分けルールは、以下が一例です。
| ボールペンの色 | 色分けルール |
| 赤 | 初めて知った部分 |
| 青 | 板書で色付きだった部分 |
| 緑 | その他ポイントだと判断した部分 |
赤ペンで記入した部分は、赤シートを使うと文字が隠れます。
活用できるように工夫してノートをまとめておくと、暗記などに役立ちます。
勉強時間がないときは青ペンで書いた部分だけ確認する、復習には赤ペンと青ペンを重点的に読み込むなど、後で見返すときに効率的に勉強できる効果があります。
また、青色には集中力を高める効果があり、緑色にはリラックス効果が期待できます。
集中力やリラックス効果が活きる確認事項や暗記項目に活用する選択肢があります。
蛍光ペンの場合
また蛍光ペンの色分けルールは、以下が一例です。
| 蛍光ペンの色 | 色分けルール |
| 赤 | 覚えるべき単語 |
| 青 | 補足説明の部分 |
| 黄 | 重要ポイント |
蛍光マーカーは余計に塗り過ぎず、重要な部分だけ色を付けるのがポイントです。
カラフルに塗り過ぎると、見返したときにどこが重要なのかわからなくなってしまいます。
少しだけ強調したい部分には、シャープペンシルや黒ボールペンで丸をつけたりアンダーラインを引いたりする方法もあります。
また蛍光マーカーは、落ち着いた色味で揃えるのもひとつの手です。
ノートを色分けするメリット
ここからはノートを色分けするメリットを、以下の3点から紹介します。
- 分類することで覚える場所がわかる
- 視覚から情報が入る
- 勉強のモチベーションにつながる
メリットを把握して、色分けをうまく活用したノートづくりを行いましょう。
分類することで覚える場所がわかる
ノートを色分けするメリットは、色によって分類ができることです。
色で分類することで重要ポイントをパッと見たときに判断でき、効率的に勉強が進みます。
例えば、初めて聞いた部分を色分けしている場合、一から覚えるべき部分だと判断できます。
初めて習った箇所は入念に勉強すべきです。
また、板書で色が付いていた部分を色分けしている場合、きちんと復習すべきだと見分けがつきやすくなります。
先生がポイントだと述べているため、定期テストに出題される可能性があります。
色分けがうまくできていないと、ノートを一から読まなくてはならず非効率です。
もし時間がないときにノートを見返す場合、色分けした部分だけ読めば良いので、時間短縮になります。
カラーボールペンに関しても蛍光ペンに関しても、必要な部分に効果的に使うことで、ノートを使った復習が効率的に進められます。
視覚から情報が入る
カラーボールペンや蛍光ペンでの色分けは、視覚からも情報が入ることがメリットです。
ノートの色が付いた部分は脳が違和感を覚え、文字を認識しやすくなる可能性があります。
例えばシャープペンシルや黒のボールペンで書いたノートの中に、赤色や青色の文字が入るとその部分だけが浮き出て見えやすくなります。
ノートを読み返すときに、色付けした部分は意識しなくても印象が残る可能性があります。
つまりノートの色付けは無意識のうちに頭に印象を与え、知識習得の手助けをしている可能性があるため、効果的に行うことが重要です。
勉強のモチベーションにつながる
ノートを色付けすることは、勉強のモチベーションアップにつながる点も魅力です。
ノートが見やすいだけで、復習の集中力アップにつながるからです。
黒だけで仕上げられたノートは見づらくなりがちで、見返したときに内容が頭に入ってこない可能性があります。
またノートの色分けを定着させることで、「しっかりノートを付けなければ」と授業に気合が入り、熱心に授業を聞く意識が働きます。
その際はノートをまとめること自体が目的にならないように、授業内容を理解することを意識したいものです。
その他ノートづくりのコツ
ノートづくりのコツはペンの色分け以外にもさまざまあります。
ここではノートづくりのコツについて、以下の4点から解説します。
- ノートづくりは丁寧に行う
- 自分が見やすいノートを作ることを目的にする
- 余白を多めにとる
- コーネル式ノートを実践する
1点ずつ詳しく確認していきましょう。
ノートづくりは丁寧に行う
ノートづくりは丁寧に行うことがポイントです。
丁寧に作られたノートは、参考書の代わりになるからです。
自分が知らなかった部分や先生が板書していた部分を強調して書き、自分専用の参考書に仕上げられます。
またノートを丁寧に作ることは重要ですが時間を掛け過ぎるのもよくありません。
学校にいる間に大部分はまとめてしまうなどのルールを設けると、帰宅後はほかの勉強に時間を費やすことができます。
自分が見やすいノートを作ることを目的にする
自分が見やすいノートを作ることを目的にしましょう。
ノートをまとめる理由は、自分自身が復習に活用するためです。
したがってノートは映えるように完璧に仕上げるよりも、見返したときに読みやすいか、授業の内容がしっかり書かれているかが重要です。
ノートには板書だけでなく先生の言葉も聞き逃さないように、しっかりとメモすることを心掛けましょう。
授業が終わった後、わからなかった部分を先生に聞いたり単語帳で調べたりして追加で書き込むと、より質の高いノートに仕上がります。
自分が復習しやすいオリジナルのノートを作成することが大切です。
余白を多めにとる
ノートづくりのポイントのひとつは、余白を多めにとることです。
後で追加情報を書き込むことができ、自分にとってわかりやすいノートづくりが可能となります。
すでに文字が埋め尽くされているノートの場合、追加で書き込むスペースが少ない上に、ノートが読みにくくなってしまいます。
ノートづくりは、板書を写したり先生の話を聞いたりすることに必死です。
したがって後で読み返したときに、ノートに書き写した内容の意味がわからないことがある可能性があります。
そういったときに余白を設けておくと、新しい情報やアイデアを書き込むことができます。
コーネル式ノートを実践する
ノートづくりのコツとして、コーネル式ノートのとり方を実践してみましょう。
コーネル式ノートとは、ノートを「➀ノート」「②キーワード」「③サマリー」の3つのエリアに分ける方法です。
「ノートに自分で線を引く」または「コーネル式ノートを購入する」のどちらを選択しても構いません。
| ②キーワード | ➀ノート |
| ③サマリー | |
書き方として、まず教科書の一段落を読み込み「➀ノート」に略語や図、箇条書きなどを使って簡潔にまとめます。
必要な情報を書き留めることを意識しましょう。
そして「②キーワード」に、「➀ノート」が解答になるような問題を書きます。
記憶が新しいうちに取り組むことが大切です。
最後に「③サマリー」には、覚えた内容を簡潔に書きます。
コーネル式ノートは復習に役立つノートで、板書を書き写すときにも活用できます。
インプットだけでなくアウトプットを組み合わせているので、知識が定着しやすいです。
医学部合格を目指すなら京都医塾へ
受験勉強では、ノートづくりも大事ですが、効率的な勉強環境選びも重要です。
医学部専門予備校の京都医塾では、生徒にとって最適な学習内容を提案し、予習・復習などの課題のバランスをとってサポートしてくれます。
合格を可能にするオリジナルのオーダーメイドカリキュラム
京都医塾では、生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイドカリキュラムを提供しています。
完全1対1の個別授業とレベル別集団授業の両方を組み合わせて受講可能です。
個別授業ではほかの生徒とスピードを合わせる必要がなく、自分のペースで勉強することができます。
苦手科目や間違いやすい箇所について丁寧に指導が受けられるため、疑問や不安が残ることがありません。
また集団授業は、各科目の習熟度に合わせたレベル別のクラスで授業が受けられます。
例えば、得意科目は一番上のクラス、苦手科目は一番下のクラスという組み合わせができるので、学力が合う環境で勉強ができます。
集団授業はほかの生徒の頑張りを間近で見られて、競争心が備わることも魅力のひとつです。
集中して学習に励める個人専用のブースを完備
京都医塾では集中して勉強できる個人ブースを完備しています。
個人ブースは1人に1つ用意していて、朝8時から退出するまで利用可能です。
自分だけの第2の勉強部屋ともいえるでしょう。
個人ブースは自習室として利用する以外にも、個人授業や課題学習を行うことが可能です。
授業の度に教材を移動させる必要がなく、勉強だけに熱中できる環境といえます。
そして個人ブースは充分な広さと収容力を備えているので、快適に勉強することができます。
半個室となっているので、壁にメモを貼ったり疲れたらストレッチで体をほぐしたりと、自由な使い方が可能です。
いくつも並ぶ個人ブースを毎日目にすることで、「ライバルに負けないぞ」という気持ちが芽生えてくると好評です。
学習用iPadのデータを活用し自習時間もサポート
京都医塾では生徒全員に学習用iPadを配布し、効率的な学習のサポートを行っています。
iPadを活用して授業を行うため、集団授業と個人授業が連携し、個人授業で集団授業の内容を質問することが可能です。
学習進捗や結果などがデータに蓄積されていくため、苦手科目や苦手箇所を分析することができます。
生徒が今取り組むべきことが明確になり、効果的な勉強時間が実現します。
また、iPadのアプリを活用してテキストの閲覧や課題の提出が可能で、身軽に勉強できる点がメリットです。
ノートを印刷して壁に重要事項を貼り出すなどの活用方法もあり、現代的な勉強方法を組み合わせ、効率的に受験勉強が進められます。
まとめ
ノートをまとめるときの色分けは、カラーボールペンと蛍光ペンそれぞれ3色程度に絞るのがおすすめです。
復習が効率的に進められるように、自分が使いやすいルールを作ることが大切です。
今回の記事ではペンの色分け以外にも、ノートづくりのコツを紹介しています。
気になる方法を試してみて、自分に合うようにアレンジしてみてください。
医学部専門予備校の京都医塾では、「一泊二日医学部合格診断」を行っており、交通費・宿泊費が無料で体験授業と学力診断テストを受けることが可能です。
ぜひお気軽にお申し込みください。