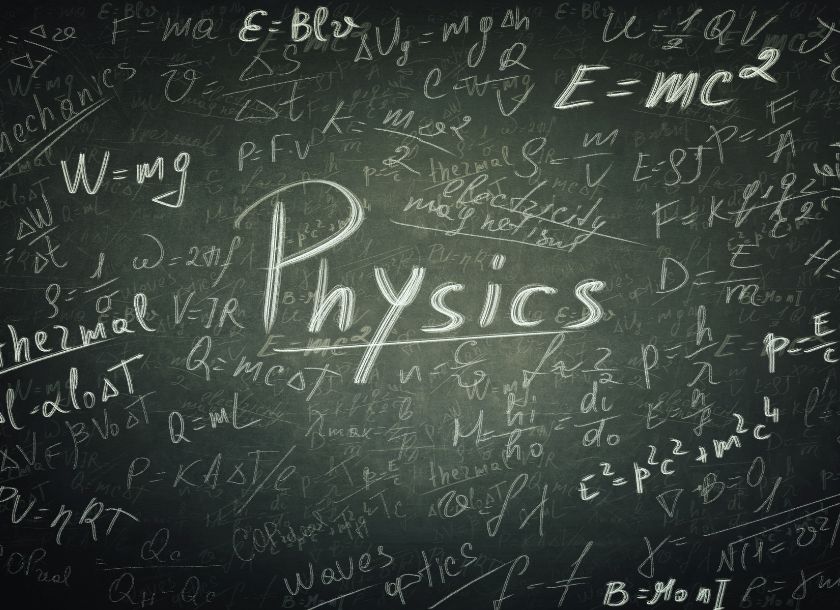「医学部受験に向けて勉強を始めたけれど、物理と生物、どちらを選べばいいのか迷っている」
「受験を突破できるのはもちろん、入学後のことも考えると、結局どちらが有利なんだろう」
このような不安や疑問を抱える医学部受験生は少なくありません。
医学部受験において、理科の科目選択は、合否を大きく左右する重要な要素の一つです。
今回の記事では、物理と生物それぞれの特徴を比較しながら、受験対策だけではなく、入学後の学習を含めたメリット・デメリットを詳しく解説します。
さらに、将来を見越した科目選択のポイントについても分かりやすくお伝えします。
自分に合った科目選択で、医学部合格への確かな一歩を踏み出しましょう。
目次
医学部受験で物理を選択すると入学後は不利になる?
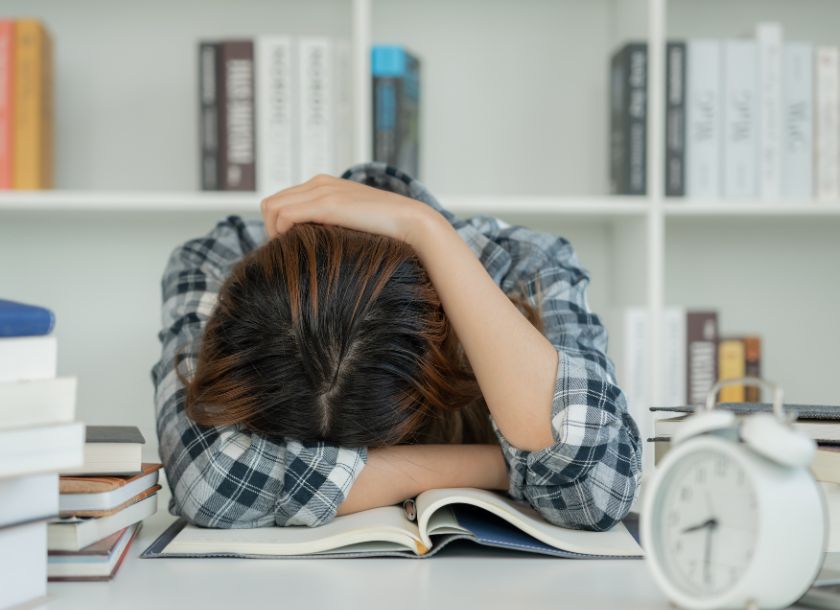
「医学部では生物の知識が必要だから、物理を選択すると不利になるのでは」と考える受験生もいるかもしれません。
しかし、実際には多くの医学部合格者が物理を選択しています。
ここでは、物理と生物を選択した合格者の割合と、選択科目が入学後の学習に与える影響について解説します。
医学部受験における物理と生物の選択割合
「物理を選択すると医学部入学後に不利になるかも」と心配する受験生もいるでしょう。
たしかに、医学部では生物に関する深い知識が求められるため、高校で生物を学んでいないことに不安を感じるのも無理はありません。
しかし、実際には多くの医学部受験生が物理を選択して合格しています。
大手予備校のデータによれば、医学部合格者のうち物理選択者の割合は約60%、生物選択者の割合は約40%と、物理選択者がやや多い傾向が見られます。
つまり、医学部合格者の半数以上が、高校で物理を選択していたという事実があります。
物理を選択しても医学部入学後不利にはならない理由
では、なぜ物理選択者が多いのでしょうか。それは、物理を選択しても医学部入学後に不利になるわけではないからです。
たしかに、医学部の授業では生物の知識を基礎とする部分があります。
しかし、大学で学ぶ生物は高校とは異なり、より専門的で高度な内容です。
高校で生物を履修していなくても、大学入学後に学習すれば追いつくことが可能です。
重要なのは、「物理と生物のどちらを選択すれば、より効率的に学習を進められるか」という視点です。
それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、自分の得意科目や興味に応じて選択することが大切です。
【物理選択】受験や医学部入学後のメリット・デメリット
物理を選択した場合、受験や入学後にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
物理選択のメリット
物理を選択するメリットとして、以下の点が挙げられます。
暗記量が少ない
物理は公式や法則を理解し、応用して問題を解く科目です。
生物に比べて暗記する内容が少ないため、暗記が苦手な人にとって取り組みやすいと言えます。
高得点を狙いやすい
物理は計算問題が中心のため、解法を理解していれば高得点を獲得しやすい科目です。
大学入学共通テストの平均点も、物理の方が生物よりも高い傾向にあります。
(参考:共通テスト 受験者数・平均点の推移(本試験) | 独立行政法人 大学入試センター)
進路の選択肢が広がる
物理は、医学部以外の理系学部でも重要視される科目です。
工学部や理学部などの受験も視野に入れている場合、物理を選択しておくことで将来の選択肢を広げられます。
また、一部の国公立大学医学部では個別試験で物理が必須科目となっています(例:九州大学医学部)。
志望校の入試科目を確認し、必要に応じて物理を選択しましょう。
(引用元:九州大学医学部医学科│入試情報(個別学力検査実施教科・科目等))
物理選択のデメリット
一方、物理を選択するデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
高い計算力が求められる
物理は数学的な要素が強い科目です。そのため、計算が苦手な人にとっては、物理の学習はハードルが高いと感じるかもしれません。
入学後に活用する機会が少ない
医学部の専門科目で物理の知識を直接活用する場面は多くありません。
しかし、物理的な思考力や論理的思考力は、医師として必要不可欠な能力です。
入学後にクラス分けがある
大学によっては、入学後の教養科目としての物理の授業で、物理選択者と生物選択者でクラスが分かれる場合があります。
【生物選択】受験や医学部入学後のメリット・デメリット
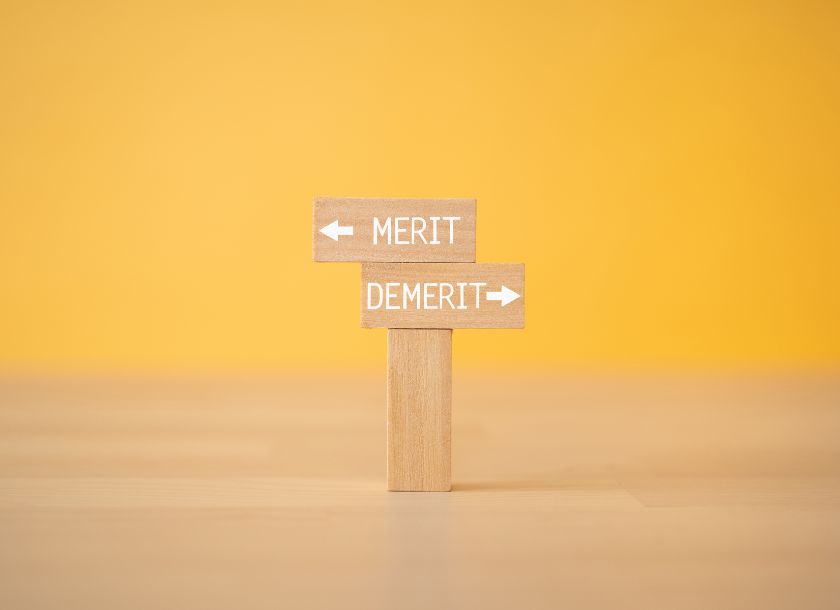
次に、生物を選択した場合のメリット・デメリットを見ていきましょう。
生物を選択するメリット
生物を選択するメリットとして、以下の点が挙げられます。
安定した得点源になる
生物は幅広い分野から出題されるため、苦手分野があっても他の分野でカバーしやすいという特徴があります。
基礎知識をしっかり固めておけば、安定した得点につながりやすいです。
化学との関連性がある
生物には化学の知識を必要とする分野も含まれています。
化学を選択している場合、学習内容の関連性を活かして効率的に学習を進められます。
入学後も知識を活かせる
生物で学ぶ内容は、解剖学、生理学、薬理学など、医学部の専門科目と深く関連しています。
入学後の学習をスムーズに進められるのは大きなメリットです。
生物を選択するデメリット
一方で、生物を選択する場合には、以下のようなデメリットも存在します。
暗記量が多い
生物は暗記する内容が多いため、暗記が苦手な人にとっては負担となる可能性があります。
似たような用語も多いため、混同しないように注意が必要です。
記述問題も出題される
生物では、知識を問う問題だけではなく、実験結果などを分析して論述する記述問題も出題されます。
そのため、単に知識を暗記するだけではなく、論理的思考力や表現力も求められます。
満点が取りにくい
生物は広範な分野から出題されるため、満点を取るのは難しいと言われています。
バランスよく学習し、8割程度の得点率を安定して取れるようにすることが大切です。
医学部入学後を考慮した科目選択のポイント
物理と生物、それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、最終的にどのような基準で科目を選択すれば良いのでしょうか。
ここでは 医学部入学後を考慮した科目選択のポイントを3つご紹介します。
将来の進路を考慮する
「まだ将来のことは具体的に決まっていない」という人も多いでしょう。
しかし、少しでも医学部以外の進路を視野に入れている場合は、物理を選択しておくとより幅広い選択肢を残せます。
また、医学部に入学して基礎医学や臨床医学以外の分野に興味を持つ人もいます。
例えば、医用工学や放射線医学など、物理の知識が役立つ分野もあります。
得意科目を活かす
物理と生物、どちらの科目が自分の得意分野なのかを考えることも大切です。
暗記が得意な人は生物、計算問題が得意な人は物理を選択するなど自分の強みを活かすことが合格への近道になります。
モチベーションを維持できる科目を選ぶ
医学部受験の勉強は長期戦です。
モチベーションを維持するためには、興味を持って学習できる科目を選ぶことが重要です。
物理や生物の学習内容に興味があるかどうかも、科目選択の判断材料にしましょう。
医学部合格を本気で目指すなら医学部専門予備校の「京都医塾」

最後に、医学部合格を本気で目指すなら、医学部専門予備校がおすすめです。
中でも、「京都医塾」は医学部受験に特化したカリキュラムと豊富な合格実績で知られています。
一人ひとりに合わせたオーダーメイドカリキュラム
今回の記事では、科目選択において「自分の得意を活かす」「モチベーションを維持する」ことが重要だと述べました。
京都医塾では、生徒一人ひとりの学力や目標、得意不得意を徹底的に分析し、完全オーダーメイドのカリキュラムを作成します。
自分に合ったカリキュラムで学習を進めることで、常に最適な学習方法で、高いモチベーションを維持しながら、効率的に学力を伸ばすことができるのです。
13名の講師陣によるチーム指導と手厚いサポート
京都医塾では、生徒一人に対し、平均13名の講師陣がチームを組み、多角的な視点から指導することで、単なる知識の詰め込みではなく、医師としての資質を育成します。
また、受験勉強が長期戦であることを踏まえ、入試直前期の不安など、精神面まで含めた手厚いサポート体制を整えています。
勉強だけに集中できる学習環境
京都医塾は、学習環境にも力を入れています。生徒一人ひとりに専用の個人ブースが用意されており、朝から晩まで、個人授業や課題学習、自習に集中できる環境を提供しています。
教材などを移動させる必要もなく、まさに「第2の勉強部屋」として活用できます。周りの生徒の頑張りも刺激になり、高いモチベーションを維持しながら学習に取り組めます。
意欲の高い医学部受験生が集まる京都医塾では、質の高い授業はもちろん、同じ目標を持った仲間と切磋琢磨できる環境が整っています。
少しでも興味を持った方は、ぜひ一度京都医塾の説明会に参加してみてください。
まとめ

医学部受験における物理と生物の選択は、どちらを選んでも入学後に大きな不利になることはほとんどありません。
重要なのは、「医学部合格」という目標に向かって、自分に合った科目を選択し、効率的に学習を進めることです。
物理と生物のメリット・デメリットをよく理解し、自分の強みを活かせる方を選択しましょう。
さらに、医学部入学後の進路も視野に入れて、将来的に活かせる知識を身につけておくことも大切です。
受験勉強は長く、大変な道のりですが、自分自身の将来のために、諦めずに努力を続けていきましょう。
医学部合格を目指して頑張るあなたを、京都医塾は全力でサポートします。