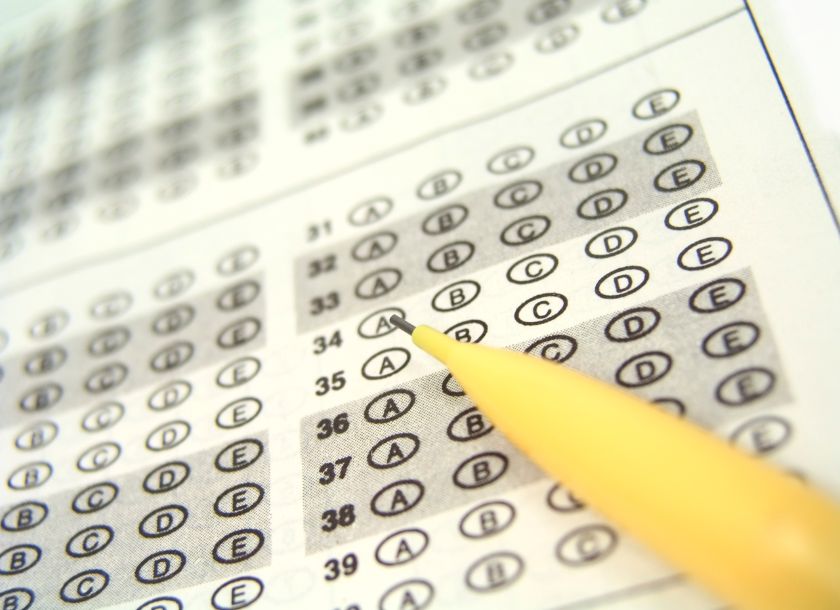2025年度から始まる新課程の共通テストは、高校教育の新しい指針に基づき、大きな変化が加わります。
新教科の追加や出題形式の見直しが行われるため、受験生にとっては戸惑いもあるかもしれません。
しかし、事前に変更点を正確に理解し、効果的な対策を立てることで、自信を持って試験に臨むことができます。
今回の記事では、新課程導入概要から変更点、さらに各科目の対策方法を詳しく解説します。
試験の準備をスムーズに進められるよう、分かりやすくお伝えしますのでぜひご一読ください!
目次
【共通テスト】新課程とは
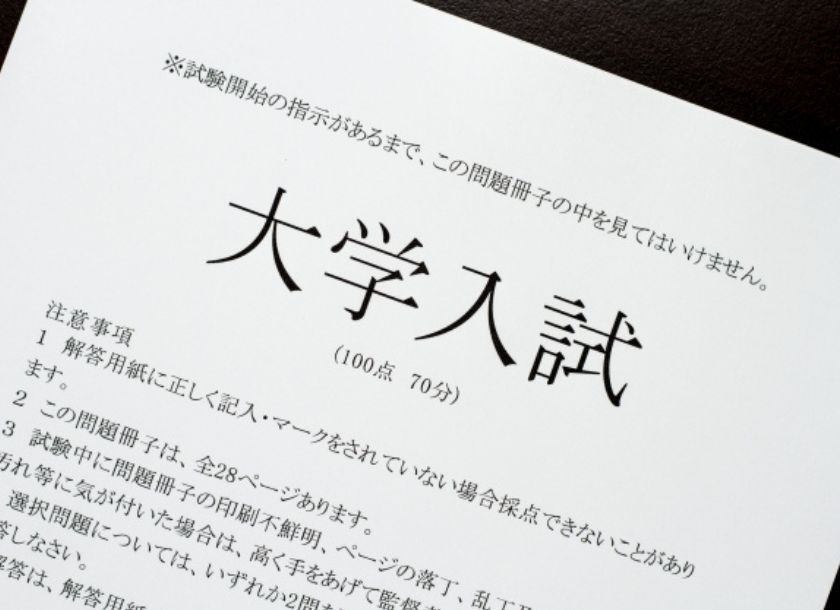
共通テストの新課程とは、2022年度から実施されている新しい学習指導要領に基づく教育カリキュラムです。
この指導要領では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性」をバランスよく育成することを目指しています。
具体的には、新教科「情報Ⅰ」の追加や、各科目の試験時間や構成が見直され、より実践的な思考力や表現力を問う内容になっています。
さらに、従来の学びを土台としつつ、デジタル社会への対応や問題解決能力を育むことが求められており、受験生にとって新たな対策が必要になるでしょう。
この変化は、受験勉強の進め方に大きな影響を与えるため、早めに詳細を把握し準備を進めることが大切です。
【共通テスト】新課程入試のスケジュール
新課程は、2022年度に高校1年生のカリキュラムからスタートしました。
この新しい学習指導要領に基づく教育を受けた最初の世代が、2025年度の共通テストを受験します。
導入の流れは次の通りです。
2022年度:新課程が高校1年生でスタート
2023年度・2024年度:新課程の2年生、3年生が順次学びを進める
2025年度:共通テストで新課程に完全移行
2025年度の共通テストは「2025年1月18日(土)・19日(日)」の2日間にわたって実施されます。
試験時間や構成に変更があるため、詳細なスケジュールはしっかりと確認しておきましょう。
【共通テスト】新課程入試の変更点

2025年度からスタートする新課程入試では、試験内容や科目構成に大きな変更が加わります。
ここでは、各教科の主な変更点を解説します。
「情報Ⅰ」が新設
新課程入試で最も注目されるのは、新科目「情報Ⅰ」の追加です。
情報社会の進展に伴い、プログラミングや情報セキュリティ、データ分析の基礎を学び、現代社会で必要なスキルを身につけることを目的としています。
共通テストでは60分間の試験時間で、主にデータの整理や分析、プログラミング的思考力が問われる問題が予想されます。
また、他の科目と異なり、問題形式や求められるスキルがまだ十分に浸透していないため、試作問題や模擬試験を活用して実践的な練習をすることが効果的です。
「数学」で科目再編・試験時間の増加
数学では、試験内容と時間に大きな変更があります。
「数学Ⅱ・B」が「数学Ⅱ・B・C」に再編され、新たに「数学C」のベクトルや複素数平面、式と曲線が試験範囲に加わります。
問題数が増えることから試験時間も10分延長して60分から70分間となり、確かな計算力と効率的な問題処理が求められます。
問題演習を繰り返し行い、新しい形式に慣れておくことが重要です。
また、試験範囲が広がった分、日常的な学習計画をしっかりと立てることが求められます。
「国語」で試験時間・問題構成・配点が変更
国語では、従来の4大問構成から5大問構成となり、「近代以降の文章」に関する問題が新設されます。
試験時間は10分延長され80分から90分間となり、以下のような構成になっています。
論説・説明文:45点
小説・文学的文章:45点
実用的文章+図表:20点
古文:45点
漢文:45点
「実用的文章」では、グラフの読み取りなど日常生活で使用する資料や報告書を題材にした問題が登場することが予想されます。
受験生は、教科書や問題集だけでなく、予想問題やセンター試験過去問も活用して多角的な対策を進めると良いでしょう。
「地歴・公民」が6科目に再編
地理歴史と公民も、選択科目の組み合わせが新たに設定されました。
「地理総合」「歴史総合」「公共」の基本科目が必修化され、それに加えて「地理探究」や「日本史探究」、「世界史探究」などが選択可能です。
しかし、「地理総合」と「地理探究」など同じ科目名を含む2科目は同時に選べないため、志望校に応じた慎重な科目選択が必要です。
また、「現代社会」が廃止され、新設された「公共」は、政治や経済を中心に学ぶ内容となっています。
この再編成によって、受験生は従来以上に幅広い視野で社会科を学ぶ機会を得る一方、選択肢が増えたことで、効果的な学習計画がより重要となっています。
以下の表は、2科目選択時の組み合わせ可能なパターンです。
| 地理総合,地理探究 | 歴史総合,日本史探究 | 歴史総合,世界史探求 | 地理総合/歴史総合/公共 | 公共,倫理 | 公共,政治・経済 | ||||
| 地理総合/歴史総合 | 地理総合/公共 | 歴史総合/公共 | |||||||
| 地理総合,地理探究 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 歴史総合,日本史探究 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ||
| 歴史総合,世界史探求 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ||
| 地理総合/歴史総合/公共 | 地理総合/歴史総合 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | |||
| 地理総合/公共 | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ||||
| 歴史総合/公共 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 公共,倫理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 公共,政治・経済 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
※本記事の内容は執筆時点の情報をもとに作成されています。最新の試験内容や詳細な選択ルールについては、必ず公式情報をご確認ください。
浪人生への経過措置
2025年度入試では、新課程履修者と旧課程履修者が混在することを考慮し、旧課程を学んだ浪人生に対する経過措置が設定されています。
例えば、数学や地歴公民では旧課程の内容をベースにした問題が出題される「経過措置科目」を受験することが可能です。
ただし、国語や理科、外国語では経過措置科目が設定されていないため、注意が必要です。
さらに、この経過措置は2025年度入試に限られており、2026年度以降はすべての受験生が新課程に基づいた試験を受けることになります。
【共通テスト】新課程入試への対策方法
新課程入試に対応するには、各科目の特徴や変更点を正確に理解し、それに応じた学習計画を立てることが大切です。
ここでは、主要科目ごとの対策方法を解説します。
「情報Ⅰ」の対策ポイント
「情報Ⅰ」は初めて試験範囲に含まれる内容のため、以下のような学習ステップがおすすめです。
教科書を中心に基礎固め
教科書を中心に学校で使われている教材をしっかり理解しましょう。
特に、アルゴリズムやプログラムの考え方、セキュリティ関連の基礎知識は重点的に押さえてください。
問題演習で形式に慣れる
試作問題や模試を活用し、実際の試験形式に慣れることが重要です。
例えば、グラフや表を活用した問題や、情報リテラシーを試す設問が出る可能性があります。
身近な例で実践力を高める
日常生活で情報技術がどう使われているかに注目すると、理解が深まります。
例えば、SNSやオンラインショッピングでの情報の扱い方を観察することも有効です。
「数学」の対策ポイント
新課程の数学では、特に「数学Ⅱ・B・C」で範囲が広がったことが注目されます。
新範囲の「数学C」に注目
ベクトルや複素数平面といった数学Cの内容が試験範囲に加わります。
これらは難易度が高い単元のため、教科書の基本問題から始め、応用問題に進む流れが適切です。
選択問題に備えた演習
「数学Ⅱ・B・C」では選択問題が設けられています。
どの単元を選ぶかを早めに決め、それに絞って対策を進めると効率的です。
試験時間に慣れる練習
試験時間が70分に延長されたため、時間配分を意識した模試や過去問演習が重要です。
問題を解くスピードと正確さをバランス良く鍛えましょう。
「国語」の対策ポイント
国語では、「近代以降の文章」を含む問題が追加され、特に実用的文章の扱い方をマスターすることが得点アップのポイントです。
実用的文章の読解力を磨く
報告書や説明文にグラフや図表が組み合わさった問題が出る可能性があります。
日常的に新聞記事や資料を読み、要点をつかむ練習をすると良いでしょう。
問題形式の変化に対応
新形式の第3問では、複数の資料を比較・解釈する力が求められます。予想問題や模試を活用して、出題形式に慣れておくことが大切です。
90分の試験時間に合わせた練習
試験時間が10分延びたことで、解答ペースを考える必要があります。
時間を計りながら模試に取り組み、全問解き終える感覚を身につけてください。
「地歴・公民」の対策ポイント
地歴・公民は、科目選択ルールが複雑になったため、選択する科目に応じた対策が必要です。
選択科目を早めに決定
新課程では6科目の中から最大2科目を選択しますが、組み合わせの制限があります。
志望校の科目要件を確認し、どの科目を選ぶかを早めに決めましょう。
基礎を徹底的に固める
地歴総合や公共など、基礎科目が試験範囲に含まれています。
教科書や資料集を活用し、基礎知識をしっかり定着させることが得点力向上につながります。
過去問と試作問題の活用
地歴・公民では、出題傾向をつかむために過去問や試作問題を解くことが有効です。
ただし、新課程初年度では過去問が少ないため、予想問題も併用して学習を進めましょう。
■本気で医学部合格を目指すなら京都医塾
京都医塾がどのようにして医学部合格を目指す生徒を支えているのか、その特徴や強みについて詳しくご紹介します。
医学部合格に向けて、新課程入試の情報をいち早く把握&対策することが必要
2025年度の新課程入試では、試験内容や科目構成が大きく変わるため、医学部志望者にとって、情報を正確かつ迅速に把握することが合格への第一歩です。
京都医塾では、独自の情報収集ネットワークを活用し、最新の入試傾向や出題予想を元にした指導を行っています。
さらに、年間学習量3,500時間を可能にする効率的なスケジュール管理を行い、重要科目での得点アップを図ります。
受験は全科目でバランスよく得点できる対策が必要であるため、京都医塾では科目間の配分を細かく調整し、最適な学習計画を提案しています。
個別カリキュラムで一人ひとりの合格戦略を立てる&進捗管理
医学部受験生の学力や得意不得意はさまざまです。そのため、京都医塾では個別カリキュラムを作成し、一人ひとりに最適な合格戦略を立てます。
例えば、得意な英語は上位クラス、苦手な化学は基礎から徹底的に学ぶなど、科目ごとに異なるレベルで学習できる柔軟な仕組みが特長です。
また、担任講師が週1回のカウンセリングを実施し、生徒の学習進捗や生活リズムを管理します。
さらに、進捗報告書や保護者面談を通じて、保護者とも密に連携し、安心して受験生活をサポートできる体制を整えています。
基礎に不安がある場合は個人授業でしっかりサポート
医学部受験では、高いレベルの応用力が求められる一方で、基礎が不十分な場合はその克服が最優先です。
京都医塾では、完全1対1の個人授業を提供し、生徒一人ひとりの弱点を徹底的にフォローします。
また、社員講師が常に校舎に常駐しており、疑問が生じた場合にすぐ質問できる環境を整えています。
このように、学習効率を最大限に高めるサポートが受験生にとっての大きな安心材料です。
まとめ
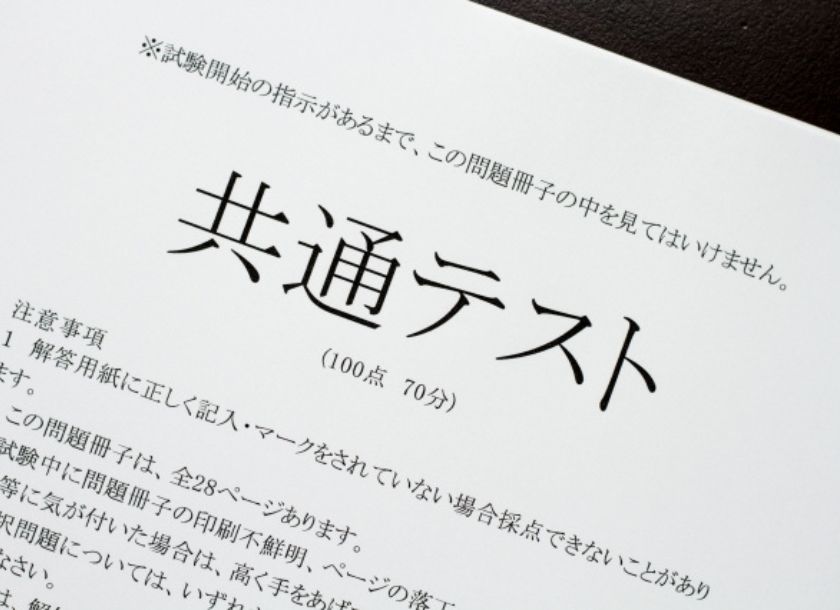
2025年度から始まる新課程入試は、受験生にとって大きな転換点です。
各科目でこれまでと異なる対策が必要になるため、効率的な学習計画と情報収集が欠かせません。
また、浪人生に対する経過措置も2025年度に限られるため、今年度中に勝負をかける覚悟が求められるでしょう。
一人で悩むよりも、専門的なサポートを活用しながら、焦らず地道に努力を重ねてください。
新課程という新たな挑戦の中で、しっかりと準備を整え、自信を持って本番に臨みましょう。